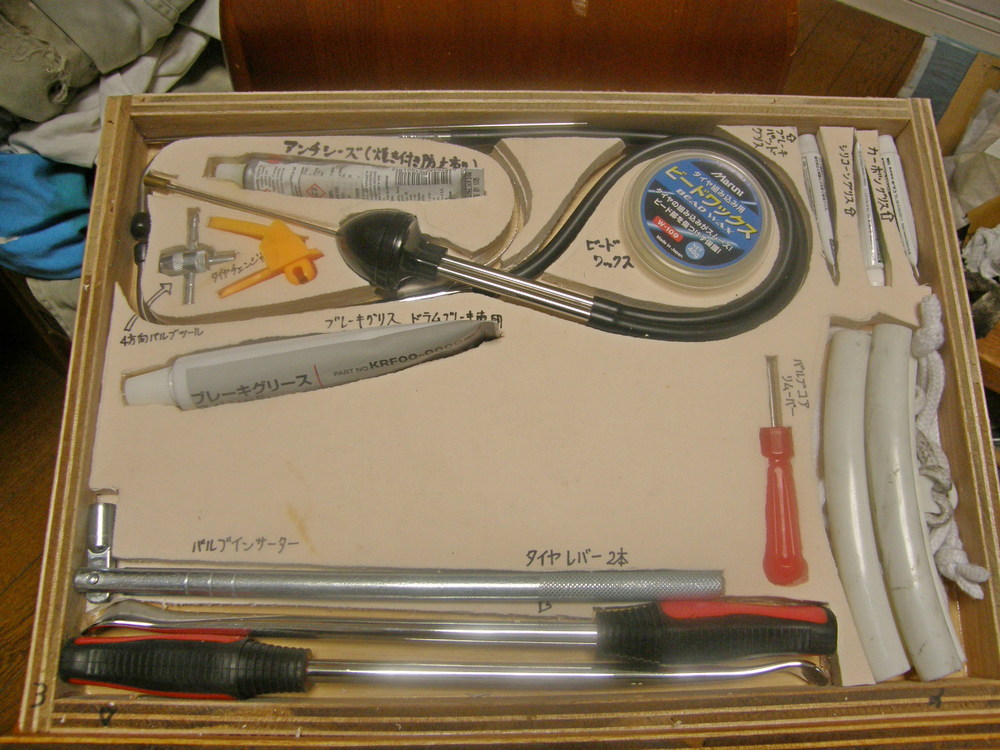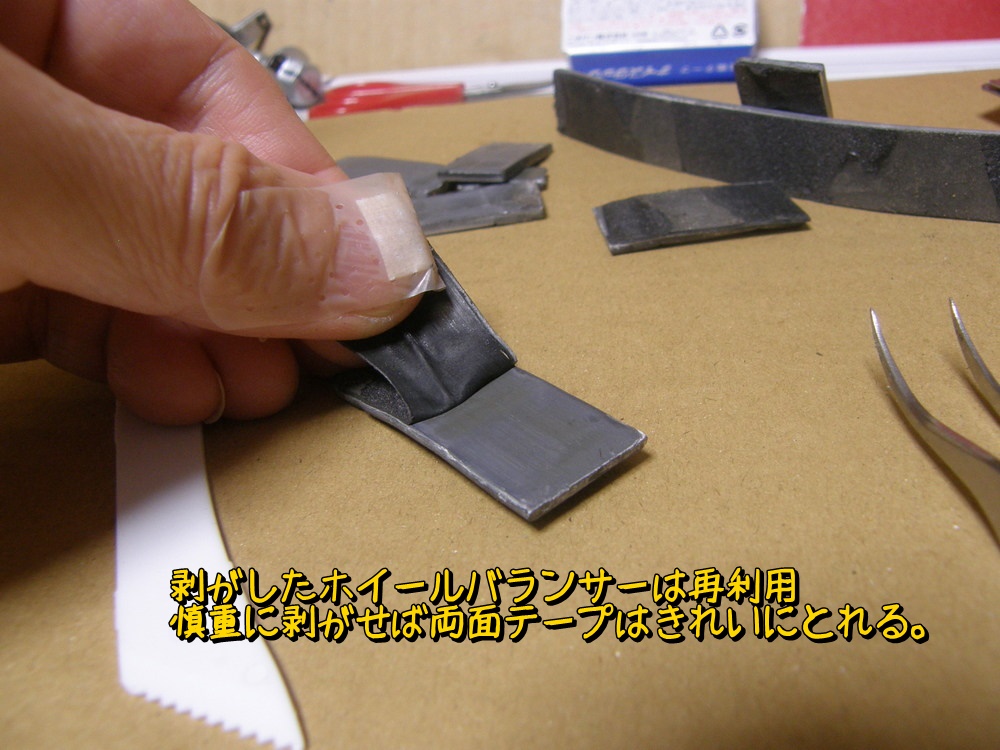■2022年11月
気が付けば肌寒くなってきて自動車いじりには絶好の季節になった。もう少し季節が進み寒くなると塗装には向かない季節になる。その前に実施すべき作業がある。ヘッドライトの研磨&クリア塗装である。アイちゃんも14年目となりヘッドライトがかなりくすんでいるのだ。

黄ばんでいるというより表面がすりガラスのようになっている感じだ。光の角度によっては表面の傷が良く見える。夏前に塗装用のクリアを購入していたので、このタイミングで研磨とクリア塗装を実施する。

ヘッドライトを外して家に持ってくる。うん、単体で見るとほんと汚い。

表面のマクロ撮影。透明には見えない。

#240の耐水ペーパーで表面を一皮むく気持ちで研磨していく。はじめは茶色い削り粉が出てくる。

だんだんと削り粉が白くなってきて、表面の汚れた面(劣化した面)が剥けたという感じになる。耐水ペーパーの番手を少しずつ上げてどんどん研磨していく。

#400の耐水ペーパーで研磨し終えた様子。透明度がなくなってしまい元のきれいなライトに戻るのか不安になる。

#1000まで研磨した様子。少しずつヘッドライトの中が見えるようになってきた。

#2000での研磨が終えるとかなり透明度があがった。これで研磨前の汚れたライトの状態に戻った感じ。耐水ペーパーをどれくらい消費するのかよくわからなかったので、各番手を2枚づつ購入していたが、実際は1枚使うか使わないかという感じ。

ネットのブログ等に掲載されている先人たちにならっての作業であるが、耐水ペーパーでの研磨後にコンパウンドでさらに磨きこんでいる人が多い。私的にはあまり表面を磨くとクリア塗装のノリが悪くなるような気もするし、めんどくさいという怠惰な気持ちもあり、#2000での研磨後にクリア塗装することにした。

クリア塗装はこの弱溶剤2液ウレタンスプレーのクリアを使用。ヘッドライトカバー(ポリカーボネート)にはラッカー塗装などはダメみたいで、この弱溶剤を使うのが必須らしい。先人の情報にはほんと感謝である。

塗装前にレバー部をグイっと引くとブシューと内部で2液が混合する。エポキシ接着剤みたいな感じだ。2液ウレタン塗装は学生時代にバイクのタンク塗装に使ったことあるので、なつかしい感じ。いったん2液を混合すると塗料の硬化が始まるので一定時間内に塗装を終える必要がある。たしか10時間ほどだったと思うけど、とにかく何日にも分けて作業するのはNGである。ノズル先端は回転させられるがどの角度にしても噴射の状態がいまいち。一般的なスプレー塗料より塗装範囲が狭い感じで、対象との距離を20cm程の近い距離で塗装した。また塗装する直前、スプレー缶にお湯をかけて容器の温度を人肌くらいまで上げると内圧が上がり塗料の噴射も細かくなる。でもお湯が容器に着いたまま塗装すると、そのお湯がしたたり落ちて塗装面についたりするので、お湯は拭き取ったほうが安心(塗装後に気が付いた)。

一度に厚塗りすると塗料が垂れるので薄く塗布する。5往復くらいでヘッドライト全体に薄く塗装できる。うすーく何度も繰り返すのが塗装が垂れないコツである。塗装毎に10分間隔を空けていけば十分乾燥するので塗料の垂れを防げる。10回くらい重ね塗りすれば塗料がなくなったので塗装時間は100分くらい。

塗装すると表面にホコリが付着し、その後その上から何度も塗装していくので、ホコリに起因する凸凹が結構できた。クリーンルームとかあればいいんだけど、まあ完全硬化後に表面研磨するのであまり気にしなくてもいい。

塗装完了。表面が多少ポツポツしてても全体を見ると透明度は非常にクリアー。ハイビームのリフレクターがすごくキラキラしていて新鮮である。

塗料が乾くまでキャンバー角調整ボルトでも取り付け遊ぼう!

ミニジャッキスタンドで馬かけ。写真で見ると地面が傾斜していることもありすごく不安定に見える。車体下にちゃんとタイヤを入れておこうね。しかしヘッドライトを外すとすごく怖い顔になるよね。

ネジ部が長いため、ソケットレンチが使えず、クローフットレンチで締めたんだけど、思いっきりナット頭なめた。扱いが雑だったこともあるが、材質が柔らかすぎではないか? これ以上ちゃんと締めれないので今回は断念して取り外す。後日よけいなネジ部を切断してソケットレンチで締めることにする。

ついでにキャリパー廻りをクリーニングしたのだが、ブリーダープラグ周辺の塗装がめくれている。フルードが付着してたんだろうね。キャリパー塗装をがんばっただけになんかショック。

ヘッドライトがないので、フロントシャーシ周辺を観察。雨の日にフロントシャーシに水が溜まるのをなんとかしたいと思っている。ヘッドライト下あたりの斜面に戸井を付けて雨水をうまく車外に流す構造にしたいと思っている。めんどくさいけどシャーシが腐ってアイ人生終了は悲しいので頑張りたい。

数時間経過しクリア塗装が大まかに乾燥したのでヘッドライトを取り付ける。まだ表面が多少べたべたしているので、塗装面に触れないように注意して作業する。うん、すごくクリアになった。 君の澄んだ瞳に乾杯!

Before/Afterの比較。ハイビームのリフレクターのキラキラ感が蘇った。

夜に走ってみるとヘッドライトの明るさが確実に向上した。いつの頃からかヘッドライトが暗いなー、こんなんだったかな?と思っていたのだが、ヘッドライトのくすみが大きな要因だったようだ。カットラインがはっきり見えるようになったし、ハイビームの光量アップもかなり感じる。塗装面はホコリの付着で結構凸凹しているが、ぱっと見はとてもクリアに見える。1~2週間して完全硬化してから表面の最終研磨しよう(しないかも)。
カットラインの様子をヘッドライト研磨の前後で比較。まず1年半前の車検前検査時。カットラインがぼやけていて、エルボー点が少しわかりにくかった。

ヘッドライト研磨後。カットラインがくっきりしてエルボー点が良くわかる。
※研磨前とはLEDバルブが変わっているけど、くっきりしたのはライト研磨が主因だと思う。

スクリーンから少し離れて運転席から撮影。カットラインが美しく見える。これだけはっきりしていると光軸調整もやりやすそう。

※雑談:雨の日の夕方家の前の漁港を散策。かなり潮位の高い満潮だったので海があふれ出しそう。シトシト雨が降っており人気もなく、波の音だけが静寂の中に流れている。家のすぐ近くなのに異世界との境界に来たような感覚になる。こういう雰囲気は好きである。自分ひとり時間軸がずれた所にいるのでは?という感覚になる。